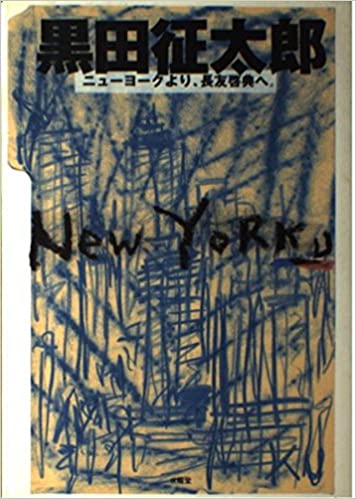twitterで福冨渉さんがラジオ番組アトロクでタイについて話をしていて、タイ文学もそのうち、そのうちと思いながら全く読めていなくて、福冨さんのやっていることに改めて感銘を受けて、自分自身の体験としてだけのタイでなくて、本や映画からもタイを知りたくなって、ラジオの中で紹介されていたプラープダー氏の本を読んでみることに。
最初のタイ文学だから嫌な印象を持って、その後読むのが億劫になるのが嫌で、とっつきやすそうな本として「座右の日本」を選んだつもりだったけど、読み始めるとプラープダーのエッセイで、ただそれはそれで、読みよすくてすぐに読み終えることができて、本人は映画を作ったり、文章を書いたりする人なので、言っていることがよく分かったのと、日本を好きなタイ人であるプラープダーとタイを好きな日本人である僕は、それぞれの国を逆から眺めているあたり面白く読み進めました。
タイはぼくを喧騒に包まれた都市に住まわせ、仕事を与え、使うお金を与え、タイ語を使わせる。日本は僕に避難所を与え、散歩の場所を与え、創造のインスピレーションを与え、価値あるナンセンスを与え、満足感を与えてくれる。
ぼくは、この時代の世界中の子供たちと同じように、物心つく前から「日本らしさ」と言うものを知っていた。人生最初の想像力の扉はメイド・イン・ジャパンで、この扉は、日本の本や歌、テレビなど、保守主義者がすぐに非難攻撃するようなぜいたくな娯楽によって開かれた。
僕は最初に日本の漫画にはまった。どういうわけか、僕くらいの世代の大人には、日本のものは想像力に悪影響を与えると言う偏見があって、今でも、最近の若者は日本の悪影響にどっぷりつかってけしからんと、愚痴のような抗議のようなことを口にする人がいる。
僕のことを本の虫だと指摘する人がいたとしても、その指摘は間違っていないと思う。ただ最初は漫画の虫から始まった。漫画を楽しむ時期があって、堅い本などの楽しみがそれに続いた。味わって食べたり、つまみ食いのようにかじったりしながら楽しみ、積み重なった本は山のようになったが、そのふもとは漫画で支えられている。
日本ほど巨大漫画産業が発展し、消費されている国はない。日本ほど大人が漫画に熱中している国もない。普通は子供が漫画に興味を示し、大人は「いつまで子供のつもりでいるの。漫画なんかもう卒業しなさい」と叱りつけるものだた、日本では大人が先を争って子供であろうとしている。これだけでも日本の特殊性(あるいは風変わりと呼んでも良い)は物語っている。
日本は子供らしさを捨てたがらない、捨てようとしない国だと言うだけでそれ以上でもそれ以下でもない。日本はピーターパンに満たされた国であり、昼も夜も夢見る子供たちでいっぱいの国であり、いつか外に飛び出してホタルを捕まえて遊ぼうなどと、窓の外を眺めて当てにならない空想にふける子供たちのいる国である。
日本が好きだと主張して、周りから疑いの目で見られたことが多々ある。というのも多くの人にとって日本は、身体は忙しく心は寂しい現代社会の代表のような国だからである。人生で勝ち残っていくためのプレッシャーと物質の飽和状態とで缶詰状態にされ、技術進歩の野心に常に覆われている。一見すれば迎合的で、心のよすがとなるものがない。日本に関する否定的な見解は枚挙にいとまがない。「ナンセンス」で子供の勉強の邪魔になるものは、アニメや漫画などの他にも、テレビゲームや電子機器、ファッションなど色々と変わった文化がある。それにカルト宗教、性に関する異常なフェティシズムなど日本の闇の部分が日本社会のイメージにもやをかけ、なんだか怪しい国だ、とされてしまうのである。しかし、そのもやは美しくもある。日本に関する見解は両極端である。水面に映る月に、無、美、真理などを読み取る深い哲学のある国とする見方を一つの極とすれば、ナイフを持った子供が友達なのかを突き刺して刺身よりも赤い血を見てしまうほど、人の神経を衰弱させる国であるとする見方がもう一極になる。
でも僕は、ほとんどの人はそんな悟りを必要としていないのではないかと思う。つまり、ほとんどの人は苦しみから解脱する必要を感じることがなく、龍安寺の石庭に15個目の石を見ることがないのである。
究極のところ家とは、心を預けておける場所、心の拠り所であれば良いのだ。心を預けておける家があれば僕らは自由になれる。
日本に行くまで、僕は座って体を洗うと言う経験はなかった。そして日本以外では座って体を洗う経験はほとんどできない。
渋谷のスクランブル交差点に代表される東京の雑踏には、いまだに慣れない。初めて東京訪れたときのショックは、今も昨日のことのように覚えている。人混みの経験がなかったわけではない。スタジアムで開かれるコンサートや、戦争反対のデモ、国を挙げての祭りなどでは、バンコクでも他人と押し合いへし合いしたものだ。でも、それは何か特別な理由があってのことで、皆が「非常事態」と納得した上での混雑だった。東京の雑踏はそうじゃない。日常の中に雑踏があり、人混みの中に生活がある。混雑に慣れているからか、他人が密集していても誰も何も気にかけない。めいめいが自分の目的に向かって一心に歩いている。雑踏の中で東京の人々は、体の周りにバリアを張って歩いているように見える。
悲しいことだけれど、日本人女性のイメージをAV女優の姿態の積み重ねで理解するタイ人男性は少なくない。AVのイメージに固執するあまり、日本人の彼女がいれば…、と夢想にふけるオタクもいる位だ。日本語を勉強したことがなくても、「やめて」「そこ」「感じる」「イク」などの単語を間接的に理解している日本語学習者の数は、これまた少なくない。
と言って僕は、エロビデオを知人の土産に買ってあげたいと思えない。陰の世界に存在するものを、あえて光に当てる必要はないと思う。暗くてよく見えない世界のものは、暗いところで目を慣らしながら見るのがまた格別と言うものである。
地震と日本は切っても切れない関係にある。いつ揺れるとしれない土地に居を構え、1秒1刻に隠された危険を承知の上で生活を営む日本人の精神力は、ぼくからすれば驚異的である。
野球の研鑽に捧げていた
何が新しくて何が古いかは、つくづくタイミングと場の問題であると思う。アーティストの作品が、時代の流れと関係なく享受されるのを知ることは、とても嬉しいことだ。作品は時代を意識していないのだから。
よしもとばななも、特定のグループ(夢見がちで寂しがり屋な女性たち)にとってはムラカミ以上にアイドルのような存在だ。
僕は文筆をなりわいとする者として、原語で書かれた小説世界の魅力を翻訳小説でも同じように楽しめるとは信じていない。特に「この作家、文章がうまいよね」などと評される時、その魅力が、翻訳を通じてどのように別の言語世界に運ばれうるのか、うまく想像がつかない。言葉を紡ぐ能力は、その言語の構造と文体を理解し、それを自由に使うことで発揮されるものだ。ムラカミを英語で読んだとき、僕は彼の文章のスタイルが好きなのか、たまたま翻訳文が好きだったのか、最後までわからなかった。ストーリーやアイディアについて興味深かったことは認める。それでも文章や文体については、それがムラカミに特有のものなのかどうか、日本語を母語としない僕にはわからなかったのだ。
翻訳とは不思議なものだ。翻訳のおかげで文章作品は海を越え、山を越えられる。でもその過程で、作家の作家性は摩耗して、平らなものになってしまうようでもある。
でも、僕が奥泉さんの講演を聞きたいと思った1番の理由は、公演後のフルートにあった。というのも、僕は普段の仕事以外のことに熱中する人物に、とても興味を惹かれるからだ。キノコマニアの音楽家ジョン・ケージしかり、夜な夜なトランペットを吹く映画監督ウディ・アレンしかり、リアルに死んだと思わせるほど完璧な瞑想のできる喜劇俳優アンディ・カフマンしかり。
文学という表現スタイルは、音楽やダンスとは全く異なる。自分を見つめ、考えながら実践していくと言う意味では共通点もあるが、実際に表現しているときには、周りに人がいても集中できない。逆に音楽やダンスなどでは、目の前に大勢の観客がいればいるほどエキサイトし、観客とコミュニケートすることで独自の一体感が生まれる。それこそライブパフォーマンスの醍醐味と言うものだろう。カートヴォネガットは音楽家に最も嫉妬を感じると言っていたそうだが僕も同感である。
タイから1歩外に出れば、そこがたとえロサンゼルスのような都市であっても(100,000人を超えるタイ人が居住し、タイの77番目の県だとも呼ばれる)
これはアジア社会において、同じくマイナーグループに属するはずの現地在住欧米人が、評論家、社会評論家、作家、テレビタレント等として活躍し、彼らの発言が現地語で流通している事と比較してみると、明らかにアンバランスである。同じように、タイで発言するタイ在住日本人評論家、日本在住タイ人タレントがいても良い。実際少しずつではあるけれど、タイに住み、タイ語で雑誌連載を書く日本人やタイの書籍を日本語に訳す翻訳家、日本文学をタイ語に翻訳するタイ人も増えてきている。言葉の垣根を取り払い、各グループ間の接着剤の役割を担う若い人の活躍が目に見えてきているのだ。
ここまで大きな都市で、チャイナタウンのない都市はベルリンぐらいしかないとのことであった。
そのせいなのだろうか。日本の街では、大人がアニメキャラクターの付いた「かわいい」ものを持ち歩いていても、あまり違和感を覚えることがない。冒頭の友人はハローキティのファイルを持ち歩く男性教師を日本の学校で見かけて、なんだか楽しい気持ちになったと言う。
彼女の自殺理由は仕事にあった。世界中の人々がスターになる日を夢見ている中、彼女は逆にその仕事が理由で私を選んだ。まるで「お金がこの世界を台無しにしている」とでも言うかのように。自殺者は自己中心的で臆病者だと言う人がいる。そして、行動の結果を熟慮できない短絡的な人間だと批判する。でも僕はそうは思わない。お金を神様と信奉して、淫乱に生きる現代人が多い中、不純な生活に吐き気をもよおし、お金に嫌気がさしてしまう人間が、果たして自己中心的な人間だと言えるかどうか。一般的に、お金がないとか、足りないからと言う理由でビルから飛び降りる人が多い中、お金に嫌気がさして命を立つ人間が、果たして臆病者と言えるかどうか。
僕は人生に必ずしも楽観的と言うわけではない(ちなみに僕は人生に対し「怠惰に懐疑的」な態度をとっている。人生に懐疑的でありながら、面倒なのでそれ以上の行動は起こさない)。と言って、人生の苦しみを自殺する形で克服しようと言う気には(まだ)なれない。それでも人によっては、人生のある時点において、自殺と言う決断が最も正しい選択肢となることがあるのだと思う。自殺は個人的なもので洋服や職業の選択と同じように、正しいとか間違っているとか、他人があれこれ言っても何の解決を生み出さない。それは自殺そのものについても言えることで、自殺が何かを改善に向かわせる事は無い。でも、その人生の終止符の打ち方には他の動物にはない人間的な魅力がある。そしてその魅力が、残されたものを思考の旅に向かわせることもある。人は嫌気のさすものを極力排除する傾向にある。自分に嫌気がさしてしまったら、自らの命を立ってそれを排除することがあっても、何の不思議なことではない。例えば、この世に醜い笑顔振りまきながら、何も感じることなく平気で暮らしている悪人のことを考えてみる。彼らのことを思うと、何も考えずに生きられることが魅力的なのかどうか、分からなくなる。それこそ不思議なことでニュースに値することだと思うのだが。
アーティストは自分のやっていることが好きだからやっているのであって、大きな美術館やギャラリーで個展を開いて有名になることが目的で表現しているわけでは無いはずだ。自分なりの表現ができて、それがある一定の人に理解してもらえたら、それで幸せを感じられると言うもの。