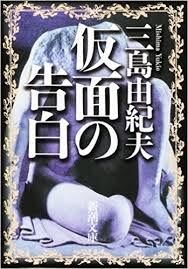積読本が溜まっているので、新しい本はなるべく買わないほうがよいのだが、プロンポンのらーめん亭へ行ったついでに、つい寄ってしまい、確か友人の一人が「仮面の告白」だったか「潮騒」が好きだといっていたようなことを思い出して。
一度読んだことがあったのだが、三島由紀夫の使う語句が今の時代にはほとんど使わないものが頻繁に出てきて、それが難しくて気づくとただ文字を追っているだけになっていて、あまり入ってこなかった。そして今村上龍の小説を読み始めたが、現代の言葉なので読みやすい。三島の「午後の曳航」は面白く読めたのだが。
きっと毒は、おみおつけに入れられたに相違なかった。
これが私の最初のejaculatioであり、また、最初の不手際な・突発的な「悪臭」だった。
私は夏を、せめて初夏をまちこがれた。彼の裸体を見る機会を、その季節がもたらすように思われた。更に私は、もっと面伏せな欲求を奥深く抱いていた。それは彼のあの「おおきなもの」を見たいという欲求だった。
しかし彼の腕に凭れて歩きながら、私の喜びは無上であった。ひ弱な生まれつきのためかして、あらゆる喜びに不吉な予感のまじってくる私であったが、彼の腕の強(きつ)い・緊迫した感じは、私の腕からの私の全身へめぐるように思われた。世界の果てまで、こうして歩いて行きたいと私は思った。
こうした屈辱を体格検査のたびに私は嘗めさせられていた。しかし今日はそれが幾分か心安くきかれたのは、近江が傍にいず私の屈辱を見ていないという安堵からだった。一瞬のうちにこの安堵が喜びにまで成長した。…
初夏の一日、それは夏の仕立見本のような一日であり、いわばまた、夏の舞台稽古のような一日だった。
級友たちの嘆声が鈍く漂った。彼の力わざへの嘆声ではないことが、誰の胸にもたずねられた。それは若さへの、生への、優越への嘆声だった。彼のむき出された腋窩に見られる豊穣な毛が、かれらをおどこかしたのである。それほど夥しい・ほとんど不必要かと思われるくらいの・いわば煩多な夏草のしげりのような毛がそこにあるのを、おそらく少年たちははじめて見たのである。それは夏の雑草が庭を覆いつくしてまだ足りずに、石の階段にまで生いのぼって来るように、近江の深く彫り込まれた腋窩をあふれて、胸の両脇へまで生い茂っていた。
たいていの乗客はひよわそうな蒼白の少年に睨みつけられて、別に怖がりもせずに、うるさそうに顔をそむけた。睨みかえす人間は滅多にいなかった。顔をそむけられると、私は勝ったと思った。こうして次第に私は人の顔を真正面から見ることができるにいたった…
私たちの腋窩には近江のそれのような旺んなものはまだ見られなかった。蘖(ひこばえ)のようなものがわずかに兆しているにすぎなかった。したがってこれまでも私も、その部分には際立った注意を払っていたわけではなかった。それを私の固定観念にしたものは明らかに近江の腋窩だった。
そこで彼のゆく道は二つしかなくなってしまう。一つはグレることであり、一つは懸命に知っているように装うことである。どちらへ行くかは彼の弱さと勇気の質が決定する問題であり、量が決定するのではない。どちらへ行くにも等量の勇気と等量の弱さがいるのだ。そしてどちらにも、怠惰に対する一種詩的な永続的な渇望が要るのである。