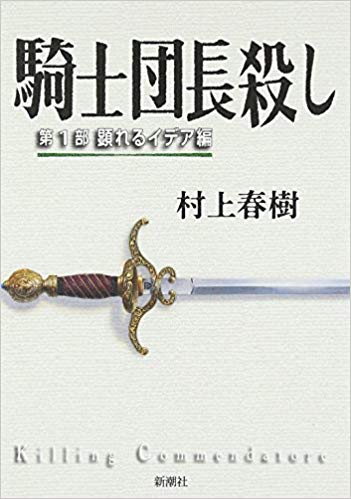なんだかんだと読んでみると面白くて、特に今回の作品は「騎士団長殺し」というタイトルから現代の生活とは関係のない内容を想像していたが、そんなことはちっともなく、また絵を確認人間にとっては興味深く読める部分がある。
そしてあえて言うまでもないことだが、無名の画家の号数の大きな抽象画を購入し、自宅の壁に飾ってくれるような奇特な人が出現する可能性はどこまでもゼロに近い。
とはいえ私は仮にも画家を志したものであり、いったん絵筆をとってキャンバスに向かうからには、それがどんな種類の絵であれ、まったく価値のない絵を描くことはできない。そんなことをしたら自分自身の絵心を汚し自らの志した職業を貶めることになる。誇りに思えるような作品にはならないにせよ、そんなものを描いたことを恥ずかしく思うような絵だけは描かないように心がけた。それを職業的倫理観と呼ぶこともあるいは可能かもしれない。私としてはただ「そうしないわけにはいかなかった」というだけのことなのだが。
ずっと奥の方までのぞき込めば、どんな人間の中にも必ず何かしらきらりと光るものはある。それをうまく見つけて、もし表面が曇っているようであれば(曇っている場合の方が多いかもしれない)、布で磨いて曇をとる。なぜならそういった気持ちは作品に自然に滲み出てくるからだ。
高度にプロフェッショナルではあるが、かといって機械的に手順をこなしているだけではない。それなりに気持ちは込めている。料金は決して安くはないが、顧客たちは文句ひとつ言わずそれを支払う。私が相手にするのはそもそも、支払い額など気にもしない人々だから。そして私の手腕は口コミで人から人へと伝わる。おかげで顧客の来訪は絶えない。予約帳はいつも埋まっている。しかし私自身の側には欲望というものが見当たらない。ただのひとかけらも。
彼女はそれについてひとしきり考えた。それから、長いあいだ水中に潜っていた人のように、水面に顔を出して大きくゆっくりと呼吸をした。
派手なオレンジ色のダウン・ジャケット、ブルージーンズ、ワークブーツという格好だった。
昔の作品では「ブルージーン」という表現を使っていたはずだが、「ブルージーンズ」に変えたのだな。
眠りたいだけ眠った。
人にいろんな側面があるように、物体にもいろんな側面がある。子供たちはその面白さをすぐに理解してくれた。
幸福な気持ちで絵を描けたとしたら、それでもうじゅうぶんではないかと私は考えていた。
そして気怠く回転する天井の扇風機を見上げながら、アイデアだかモチーフだか、そんなものがやってくるのを待ち受けた。
そこには生命の温かみがあるからだ。
もともとが謙虚な性格の人ではない。他人と穏やかで友好的な関係を維持することは、彼の得意分野ではなかった。そのようにして「孤立」がこの人の人生を貫くライトモチーフになる。
市民たちは温かいカフェの中でラム入りコーヒーを飲んでいる。
今ちょうど挽きたてのコーヒーにラムをたらして飲んでいる。
絵のモデルになるというのは、往々にして丸裸にされることでもあります ー 多くの場合実際的に、またときとして比喩的に。画家は目の前にいるモデルの本質を、少しでも深く見抜こうとします。つまりモデルのまとった見かけの外皮を剥がしていかなくてはならないということです。しかしもちろんそのためには、画家が優れた眼力と、鋭い直感を持ち合わせている必要うがあります。
一般的には膠と顔料と箔などを主に用いた絵画であると捉えられています。そしてブラシではなく、筆や刷毛をで描かれる。つまり日本画というのは、主に使用する画材によって定義される絵画である、ということになるかもしれません。もちろん古来の伝統的な技法を継承していることもあげられますが、アバンギャルドな技法を用いた日本画もたくさんありますし、色彩も新しい素材を取り入れたものが盛んに使用されています。つまりその定義はどんどん曖昧になってきているわけです。
私は長いあいだ眠っていた筋肉を叩き起こし、フル稼働させなくてはならなかった。疲れはしたが、そこにはある種の物理的な心地よさがあった。
「削り取られたのではなく、そのぶんが別の場所に移植されたのだと考えるのが、現実の世界における公式的な見解です」と私は言った。
彼が耐えきれずに射精をすると、それに合わせて彼女は異国の鳥のような声を短く上げ、彼女の子宮はそのときを待ち受けていたかのように、精液を奥に受け止め、貪欲に吸い取った。
「どう、十分硬くなったかしら?」と彼女は尋ねた。
「金槌みたいに」と私は言った。
「釘だって打てる?」
「もちろん」
世の中には釘を打つべき金槌があり、金槌に打たれるべき釘がある、と言ったのは誰だったろう? ニーチェだったか、ショーペンハウエルだったか。あるいはそんなこと誰もいっていないかもしれない。
我々が夫婦関係を正式に解消し、それからあとも友だちの関係でいられるとは、私にはとても考えられなかった。我々は結婚していた六年の歳月を通して、ずいぶん多くのものごとを共有してきた。多くの時間、多くの感情、多くの言葉と多くの沈黙、多くの迷いと多くの判断、多くの約束と多くの諦め、多くの快楽と多くの退屈。もちろんお互いに口には出さず.自分の内部に秘密として抱えていることもいくつかあったはずだ。しかしそのような隠しごとがあるという感覚さえ、我々はなんとか工夫して共有してきたのだ。そこには時間だけが培うことのできる「場の重み」が存在した。我々はそのような重力にうまく身体を適合させ、微妙なバランスをとりながら生きてきた。そこにはまた我々独自の「ローカル・ルール」のようなものがいくつも存在した。それらを全部なしにして、そこにあった重力のバランスやローカル・ルールを抜きにして、ただ単純に「良き友達」なんかになれるわけがない。
肖像画というのは基本的に、相手が描いてもらいたいという姿に相手を描くことです。相手は依頼主である、できあがった作品が気に入らなければ、『こんなものに金を払いたくない』と言われることだってあり得るわけですから。ですからその人物のネガティブな側面はできるだけ描かないようにします。良い部分だけを選んで強調し、できるだけ見栄え良く描くことを心がけます。そういう意味においてきわめて多くの場合、もちろんレンブラントみたいな人は別ですが、肖像画を芸術作品と呼ぶことはむずかしくなります。
私は六年間、ユズと共に最初の結婚生活を送っていたわけだが(前期結婚生活、と呼んでいいだろう)、そのあいだほかの女性と性的な関係を持ったことは一度もなかった。そういう機会がまったくなかったわけではないのだが、私はその時期、よその場所に行って別の可能性を追求するよりは、妻と一緒に穏やかに生活を送ることの方により強い興味を持っていた。
私はその基本線のまわりに、木炭を使って何本かの補助的な線を加えていった。そこに男の顔の輪郭が起ち上がってくるように。自分の描いた線を数歩下がったところから眺め、訂正を加え、新たな線を描き加えた。大事なのは自分を信じることだ。線の力を信じ、線によって区切られたスペースの力を信じることだ。私が語るのではなく、線とスペースに語らせるのだ。線とスペースが会話を始めれば、やがては色が語り始める。そして平面が立体へと徐々に姿を変えていく。私がやらなくてはならないのは、彼らを励ますことであり、手を貸すことだ。そして何より彼らの邪魔をしないことだ。
まず昨日木炭を使って描いた骨格から、パンの切れ端を消しゴム代わりに使って、余分な線をひとつひとつ取り去ってった。
デッサンはいわば絵画の設計図のようなものであり、そこにはある程度の正確さが必要とされる。それに比べると、クロッキーは自由な第一印象のようなものだ。印象を頭の中に浮かばせ、その印象が消えてしまわないうちに、それにおおよその輪郭を与えていく。クロッキーでは正確さよりは、バラストスピードが大事な要素になる。名のある画家でも、クロッキーがあまりうまくない人はけっこうたくさんいる。
「そしてこちらがよくよく考えているということを、相手にわからせることもまた大事だ、ということですね。ひとつの素振りとして」
「そう、そういうことだ。ファースト・オファーはまず断るというのがビジネスの基本的鉄則だ。覚えておいて損はあらない」
「ウィーンは他に類を見ない街です」と免色は言った。「そこに少しでも暮らしてみれば、すぐにそのことがわかります。ウィーンはドイツとは違う。空気が違い、人が違います。食べ物が違い、音楽が違います。ウィーンはいわば人生を楽しみ、芸術を慈しむための特別な場所です。
私と秋川笙子は居間の椅子に座って、軽い世間話(山の上での生活や、谷間の気候について)をしながらお茶を飲んだ。実際の仕事にかかるまえにそういうリラックスした会話の時間が必要なのだ。
「人物を描くというのはつまり、相手を理解し解釈することなんだ。言葉ではなく線やかたちや色で」
私は自然で活発な会話を歓迎した。