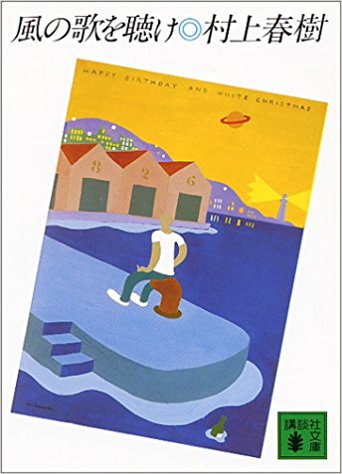それまで、村上といえば龍の方を読んでいて、春樹の方は手にとったことがなかったのだが、2006年から2008年の間にしていた世界一周の旅の中で、宿に置いてあったり、旅人と交換したり、古本屋で見つけたりして読み漁った。これまでに見かけなかった言葉選びや一風変わった比喩表現が面白かった。色彩を持たないなんたらと、騎士団なんたらは読んでいない。「鼠」やら「ジョニー・ウォーカー」やらに起こるファンタジーな出来事が好きになれない。文体が特に好きなので、「走ることについて語るときに僕の語ること」や「職業としての小説家」など新しい随筆も読んでいるし、その村上春樹節に声を出して笑ってしまうこともある。
もちろん、あらゆるものから何かを学び取ろうとする姿勢を持ち続ける限り、年老いることはそれほどの苦痛ではない。これは一般論だ。
20歳を少し過ぎたばかりの頃からずっと、僕はそういった生き方を取ろうと努めてきた。おかげで他人から何度となく手痛い打撃を受け、欺かれ、誤解され、また同時に多くの不思議な体験もした。様々な人間がやってきて僕に語りかけ、まるで橋をわたるように音を立てて僕の上を通り過ぎ、そして二度と戻ってはこなかった。
「暗い心を持つものは暗い夢しか見ない。もっと暗い心は夢さえも見ない。」死んだ祖母はいつもそう言っていた。
鼠はそれっきり口をつぐむと、カウンターに載せた手の細い指をたき火にでもあたるような具合にひっくり返しながら何度も丹念に眺めた。
まるでロールシャッハ・テストにでも使われそうなその図柄は、僕には向かいあって座った二匹の緑色の猿が空気の抜けかけた二つのテニス・ボールを投げあっているように見えた。
僕がバーテンのジェイにそう言うと、彼はしばらくじっとそれを眺めてから、そう言えばそうだね、と気のなさそうに言った。
「何を象徴してるのかな?」僕はそう訊ねてみた。
「左の猿があんたで、右のがあたしだね。あたしがビール瓶を投げると、あんたが代金を投げてよこす。」
僕は感心してビールを飲んだ。
もちろん金持ちんなるには少しばかり頭が要るけどね、金持ちであり続けるためには何も要らない。人工衛星にガソリンが要らないのと同じさ。グルグルと同じところを回ってりゃいいんだよ。でもね、俺はそうじゃないし、あんただって違う。生きるためには考え続けなくちゃならない。明日の天気のことから、風呂の栓のサイズまでね。そうだろ?」
<中略>
「でも結局はみんな死ぬ」僕は試しにそう言ってみた。
「そりゃそうさ。みんないつかは死ぬ。でもね、それまでに50年は生きなきゃならんし、いろんなことを考えながら50年生きるのは、はっきり言って何も考えずに5千年生きるよりずっと疲れる。そうだろ?」
そのとおりだった。
週に一度、日曜日の午後、僕は電車とバスを乗り継いで医者の家に通い、コーヒー・ロールやアップルパイやパンケーキや蜜のついたクロワッサンを食べながら治療を受けた。一年ばかりの間だったが、おかげで僕は歯医者にまで通う羽目になった。
右の乳房の下に10円硬貨ほどのソースをこぼしたようなしみがあり、下腹部には細い陰毛が洪水の後の小川の水草のように気持ちよくはえ揃っている。
30分ばかりしてから急に誰かに会いたくなった。海ばかり見ていると人に会いたくなるし、人ばかり見てると海を見たくなる。変なもんさ。
オーケー、一曲目。これをただ黙って聞いてくれ。本当に良い曲だ。暑さなんて忘れちまう。ブルック・ベントン、「レイニー・ナイト・イン・ジョージア」。
どんどんレコードをかける。クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル、「フール・ストップ・ザ・レイン」、乗ってくれよ、ベイビー。
「リクエスト曲はビーチ・ボーイズの<カリフォルニア・ガールズ>、なつかしい曲だね。どうだい、これで検討はついた?」
彼女は疑り深そうに肯いてから立ち上がってレコード棚まで大股で歩き、よく訓練された犬のようにレコードを抱えて帰ってきた。
<ギャル・イン・キャリコ>の入ったマイルス・デイビス。
「ねえ、もしよかった一緒に食事しないか?」
彼女は伝票から目を離さずに首を降った。
「一人で食事するのが好きなの。」
「僕もそうさ。」
「そう?」
彼女は面倒臭そうに伝票を脇にやり、プレイヤーにハーパース・ビザールの新譜をのせて針を下ろした。
「じゃあ、なぜ誘うの?」
「たまには習慣を変えてみたいんだ。」
「一人で変えて。」
「もしもし、」と女が言った。それはまるで安定の悪いテーブルに薄いグラスをそっと載せるようなしゃべり方だった。「私のことを覚えてる?」
彼女は16歳で一文無しで寝る場所もなく、おまけに乳房さえ殆どなかったが、頭の良さそうな綺麗な目をしていた。
「今日は靴を磨かなくていいの?」
「夜中に磨くさ。歯と一緒にね。」
「きっとあんたに相談したがっているはずだよ」
「何故しない?」
「しづらいのさ。馬鹿にされそうな気がしてね。」
「馬鹿になんかしないよ。」
「そんな風に見えるのさ。昔からそんな気がしたよ。優しい子なのにね、あんたにはなんていうか、どっかに悟りきったような部分があるよ。…別に悪く言ってるんじゃない。」
エプロンをつけた30歳ばかりのいかにも貧血症といった感じの女が前かがみになって…
嘘をつくのはひどく嫌なことだ。嘘と沈黙は現代の人間社会にはびこる二つの巨大な罪だと言ってもよい。実際僕たちはよく嘘をつき、しょっちゅう黙りこんでしまう。
しかし、もし僕たちが年中しゃべり続け、それも真実しかしゃべらないとしたら、真実の価値など失くなってしまうのかもしれない。
はっきりとした海の香りが感じられるあたりで倉庫街は途切れ、柳の並木も歯が抜けたように終わっていた。
私がこの三年間にベッドの上で学んだことは、どんなに惨めなことからでも人は何かを学べるし、だからこそ少しずつでも生き続けることができるのだということです。