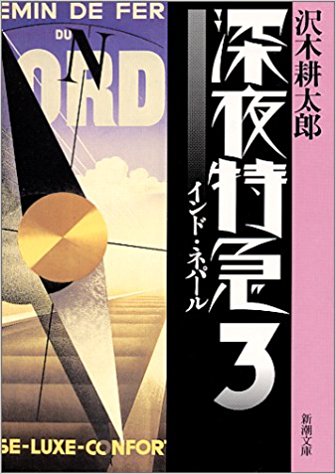セールの期間中にKEY BOOKSの本棚を見ていて、無性に読みたくなった。
インドへは4度訪れていて、合計で6ヶ月以上を過ごしていて、ネパールは2度、1ヶ月ほど。訪れた回数や時間は、その場所を身近に感じさせるもので、インドは日本とタイに続く慣れ親しんだ場所だ。
着いたとたんに見知らぬ人から声を掛けられ、いつの間にか車に乗ることになってしまい、どこをどう走っているのかもわからないまま宿に向かう。そして、公司とか大廈とかいった漢字の看板が林立する香港の街の中を走った時も、不安とは別に体の奥底から湧き上がってくる興奮を抑えきれなかったが、今またその派手で賑やかな街とは打って変わったくらい街の中で同じような興奮を覚えている。
デリーの空港にひとり降り立ったのは、夜だった。何もかもが初めてでビクビクしていた。運良く2人組の日本人を見つけて声を掛けたのだと思う。ひょっとすると掛けられたのかもしれない。空港の外にはタクシーのドライバーなのか、人を待っているのか、それにしてはずいぶんとたくさんの人がいた。周りは暗く、目だけがギョロギョロと白く光っていた。
※
仕事を始めてからは海外に出ることがなくなった。金も貯めたかったし、何よりやることがたくさんあった。数年働いて、余裕が出てからモロッコを訪れた。パリのシャルル・ドゴール空港を経由して、カサブランカまで。はじめてのアフリカ大陸だった。この時も到着は深夜だったように記憶している。空港を出るとジュラバと呼ばれるねずみ男のような服を来たドライバーに車に誘導された。タクシーはベンツだった。初めての土地だし、真っ暗だったし、空港で眠ることも考えたが、日本からの長い々々フライトで疲れていたので、「ええい、ままよ」と身を任せた。
そして、ポーターが案内してくれた部屋を見て、それはほとんど尊敬の念に近いものにまでなってしまった。
部屋に足を踏み入れたとたん、私は思わず声を出してしまった。
「凄いじゃないか!」
それは実に豪華な部屋だった。
3度目のインド。3ヶ月のインド、ネパールの旅の最後にカトマンドゥからカルカッタ行きの飛行機が遅れたか決行したかで、豪華なホテルを当てがわれた。これまでの旅を思うと信じられないような待遇であった。友人3人とプールではしゃいだ。
路地を抜け、少し広い道に出た。人通りがほとんどないため、差し込んできた陽の光にミルク色の朝靄が薄く色づきはじめる様がはっきりと見とおせるその道には、しかし、無数のカラスが我がもの顔にうろついていた。
サダルストリートには本当にカラスが多かった。カルカッタは好きな街で、はじめてのバックパックの時には、バンコク〜デリー〜アグラ〜バラナシ〜ポカラ〜カトマンドゥ、そしてカルカッタと1ヶ月を旅してきて、もう旅には慣れていた。毎日カレーばかりで飽き飽きしていた。おいしそうなパン屋を見つけたが、パンもピザカレーパンなど結局カレー味だった。当時カルカッタにはサトシと名乗る流暢な日本語をはなすインドの男がいて、彼が発した「もう商売火の車やねん」の言葉は忘れない。と調べてみるとyoutube動画にサトシ氏の姿があった。
「ここはなんというホテルなの?」
「サルベーション・アーミー、ホテルじゃない」
サルベーション・アーミー、つまり救世軍だ。
カルカッタを訪れた2度ともここを使った。吹き抜けのスペースがあって居心地が良かった。1度目はドミトリーのルームメイトが4人全て日本人だった。そういう風に配慮しているのかもしれない。
その男の顔にはいかにもブローカー風の卑しさのようなものがにじみ出ていた。
ふと原くんという男のことを思い出した。2度目のインドはゴアで知り合い、日本へ戻ると彼はハシシをいくらか日本へ持って帰ったらしく、その欠片を封筒に入れて僕の家に送ってよこしたのだ。嬉しくもあったが、やや神経を疑わざるをえんだろう。そして3度目のインドで再びゴアで再開。モヒカンになって少し様子が変わり、お互いの間にできる空気は前とは変わっていた。
また、近くにはニュー・マーケットというバザール風の一大商店街があり、そこに行けば日用雑貨はもちろんのこと、土産ものから禁制品まで手に入らないものはなかった。
おそらくこのマーケットの近くに映画館があり、そこでジャッキー・チェンの「Who Am I」を観た。インド人は大盛り上がりであったし、僕ともう一人の友人も大興奮で、映画館を出た後しばらくはカンフーのポーズをとって遊んだ。
薄暗い店だった。中に入ると、奥の帳場には眼つきの鋭い大柄の男が座っていた。
バラナシでガンジャを調達しようとしていた。ガンジス川沿いの怪しいレンガ造りの部屋に連れて行かれると、男と言い合いになり、僕は柄にもなく大声を出していた。いつもはやんちゃ度の強い友人が僕を間に入って僕とインド人をなだめた。結局あの男からは買わなかったのかもしれない。
一枚一枚ていねいに調べていくと、途方もなく汚れ、破れた五ルピー札が一枚混じっているのが見つかった。換えてくれと頼むと、これで使えると頑張る。それなら自分で使えばいい、俺はいらないと断固主張しても、相手も一歩も引こうとしない。
インドの汚い札は本当に汚れているし、破れて元の大きさの半分くらいになっているようなものもあった。ああいう経験が、僕の世界を広げたのではと思ったりする。これで良いのか。結局、何でもありだな、とあの頃よく思ったものだ。
私は香港以来の熱狂に見舞われ、毎日カルカッタの街をうろつき廻った。
あれは確かカルカッタでの事だったか、すり減った靴底のティンバーランドを丸ごと張り替えてもらった。もともとは良い靴だったが、少しツルツルと滑る素材で歩き慣れるまで少し時間が必要だったが、こういう体験が面白かった。
カルカッタにはすべてがあった。悲惨なものもあれば、滑稽なものもあり、崇高なものもあれば、卑小なものもあった。だが、それらのすべてが私にはなつかしく、あえていえば、心地よいものだった。
噂に聞くインドの三等とは、実際どのくらい混むものか、乗る前にいちど駅で確かめておきたかった。
はじめてのインドでアグラからバラナシへ向かう列車は最悪で、今思えば小さな不条理の洗礼を受けた。寝台の座席を予約したのだが、僕の席にはすでに老人男性が腰を下ろしている。ここは僕の席のはずとチケットを見せると、彼の番号もこの席だった。どちらが悪いわけでもなく、おそらくは僕がニセのチケットをつかまされたのだろう。まだまだ幼く甘さの目立った僕は、その事実に腹を立てて、老人に冷たく接していた。仕方なく席を半分ずつにして眠った翌朝、彼は僕に1杯のチャイをご馳走してくれた。
その初めての寝台列車で、すごかったのはインド人たちの熱い視線だ。夜は暗いし気にならなかったが、日本人が珍しいのか日中になると車内のインド人全員が僕を見た。ちらっと見るとかそういうのでなく、じーっと見ているのだ。負けじとこちらも見返して、目をそらしてもらうとするが、そんなことはお構いまし、いつまでもいつまでもずーっと見つめられていて、これには参った。
私が答えると、車夫は問題にならないといように顔をしかめ、チャロ、と低く呟いた。
チェロとかアーチャ、YESの時に首をかしげる仕草。
ブッダガヤにいる時、いまインドでは『ボビー』という映画がヒット中だと聞かされた。
インドの映画は有名だったので、ものは試しとアグラで一日中ついていてくれたリキシャーに頼んでインド映画へ連れて行ってもらった。内容は覚えていないし、面白く感じた覚えもないのだが、僕から見ればいくらか大げさに反応をしめすインド人たちを見れてよかったし、本来映画はああやってみたっていいものだよな。途中休憩があって、後半へ続くという仕組みにも驚かされ、僕は後半はパスをさせてもらった。
英語やフランス語やたぶん中国語や日本語にもあって、ヒンドゥー語にない言葉が三つあるが、それが何かわかるか。私が首を振ると、キャロラインが教えてくれた。
「ありがとう、すみません、どうぞ、の三つよ」
途中でいちど乗り換え、ネパールとの国境の街であるラクソールについたのが夜の九時。
僕が覚えているのはスノウリという国境の街。これはネパール側の街だろうか。国境を越えるだけで驚くほどに様子が変わった。人々はやさしく笑顔になり、食堂ではビートルズが流れて、ビールを出していた。わずか2週間ほどのインドで相当に疲れていた。
それはネパールの風景が僕たち日本人にとってはごく親しいものであったからかもしれません。
スノウリからポカラまでのバスがまた苛酷であった。晴れた日には、ポカラにあるジャーマンベーカリーというパン屋から雄大なマウント・マナスル、アンナプルナがくっきりと見えた。それはそれは大きく、青い山だった。
1泊山の上で泊まるだけという、簡単なトレッキングへ行った。サンダルでも登れてしまうような、そんなトレッキング。山小屋は本当に真っ暗で、小屋の中でネパール人とハシシを吸っていると、そいつが悪い奴に思え、何かされるのではという妄想にかられ、眠るしか無くなってしまった。
戻って挨拶をしようかと思ったが、こんなところはもういやだ、と叫んでいた彼より先に自分が出て行ってしまう事を考えると、顔を合わせるのが辛かった。それに、別れの挨拶と勘定は前夜のうちに済ませてあった。
思い切り手足が伸ばせる幸せを味わいながら、甲板に座ってチャイを飲み、河を渡る風に吹かれていると、カトマンズからの三十時間に及ぶ強行軍が、もうすでに楽しかったものと思えてきそうになる。なんと心地よいのだろう
三十時間とか三十六時間とかいう移動時間があるのだから、初めの頃は驚いた。それも含めて全部旅になったのだから、慣れというのは頼もしい。
しかし、私がベナレスに立ち寄ることにしたのは、ヒンドゥーの聖地としてんベナレスに関心があったからではなく、ベナレスという町がカルカッタに匹敵するほどの、猥雑さと喧騒ん満ちた町だと聞いたからだった。
インドの町の名前はこの深夜特急の頃から、そして僕が旅をしていたころから、そして今といくつか変わっている。ベナレスはバラナシ、ボンベイはムンバイ、カルカッタはコルカタなど。名前の響きか僕にとっての場所になっているので、僕にとってバラナシはバラナシであり、ボンベイはボンベイで、カルカッタはカルカッタなのだ。
私もリキシャに関しては狡(ずる)くなってきた。
狡猾という言葉をポジティブに使う人がいるが、この文字は狡いという言葉である。狡い相手には狡くやらないといけないのだが、僕は自分の誇りのために、自分のために生きる。
通りすがりの一軒の店にふらりと入ると、大衆食堂風の造りにもかかわらず、何も言わないうちから英語のメニューが出てきた。ベナレスは、聖地であるとともに、やはり観光地でもあるようだった。
バラナシの路地を歩いていると、軒を連ねる一軒の家の窓が空いていて、少年がファミコンのスーパーマリオをプレイしているのが見えた。声をかけて、ひとつやらせてみてくれ、とコントローラーを握らせてもらった。スーパーマリオブラザーズ 1−1。完璧な動きで旗を切って見せてやった。フロム・ジャパーン。
女はまずサリーを身につけたまま河に入り、口をすすぐ。ガンジス河は雨季の水を集めてかなりの速さで流れている。女が頭にかかっていたサリーをはずすと、そこに美しい銀髪が現れる。老婦人だったのだ。次に老婦人は、濁った水の中に、肩まで身を沈ませる。一度、二度、三度…。するとサリーはぴったりと体にはりつき、体の線をくっきりと浮き立たせる。老婦人ゆえの不思議ななまめかしさに息を呑む思いがする。
このなまめかしさが頭に浮かぶ。サリーの布地が水を含み体にまとわりつく感じ。年を重ねるごとに、自分と同じくらいまたはそれよりも上の女性に魅力を感じるようになった。この先きっと50代60代の女性になまめかしさを感じていくことになるだろう。楽しみだ。未だに若い女が良いと言っている男たちが多くいるようだが、なんて子供なんだろう。
ベナレスには野良の猿がいて、あちこち自由に歩いては悪戯(いたずら)をしているということだった。
バラナシで泊まった宿で、夕方の屋上にあがると猿が見られた。ハンピにもたくさんの猿がいたな。ハンピで知り合ったヴォヤンという当時のユーゴ人にかっこよさを感じて、今デザイナーという職業についているようなところがある。
やがて出てきたカレーを手で食べていると、主人が近づいてきて、どうしてスプーンを使わないのだ、と不思議そうに訊ねてきた。「ここがインドだからさ」私がいうと、彼はさも嬉しそうに笑って、そうかヒア・イズ・インディアか、と二度ほど繰り返して調理場へ入っていった。
こういうのがいいんだと思うんだ。どこかのバカがタイでの接客を「僕は説教しますよ」とか言っていたけど、なら日本に居ろよ。似合ってるぜ。
しかし、この近辺に都合よくブルドーザーなどがあるとは思えない。そのうえ、隣の乗客に訊ねると、カジュラホへ行くにはこの道しかないという。残る道はサトナに引き返すことしかない。もうどうにでもなれ、と私はなかば自棄(やけ)になって目を閉じた。
同じように、もうどうにでもなれ、と自棄になって目を閉じたことがある。東欧特有の曇った空と、彼らの険しく見える顔つきや、その前にブルガリアで見ていたサッカー場でボコボコに殴られた日本人の顔や、エストニアで聞いたアジア人差別の話、それにポーランドで公園でスケッチをしていると足元にドサッと何かが落ちてくる。上を見上げるが何もなく、スケッチを続けると、またドサッと。周りをみると、ずいぶん遠くの方にまだ中学生か高校生くらいの3〜4人のグループがこちらに石だか木の実を投げてきていた。グルジアからトルコの国境に向かう列車は、待てど暮らせどやって来ない。駅員がこれだという列車は駅に入ってくるとスピードを緩めたが、停車することなく、窓から飛び乗った。車内は埃が舞い、そんな中でも一応自分の番号の席まで移動して、飯も水もなく、長い移動。疲れていた。もうどうにでもなれ、と自棄になって目を閉じた。